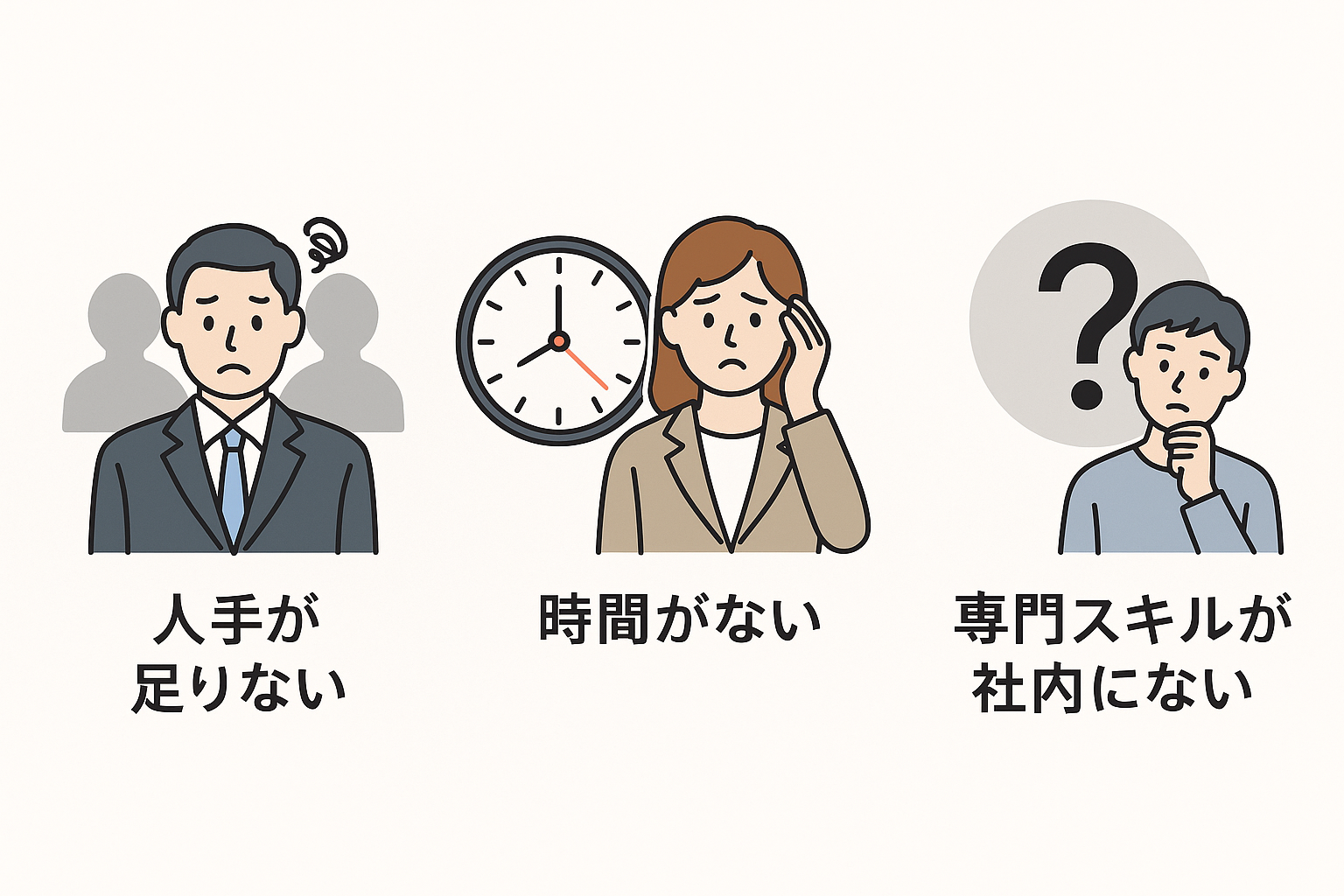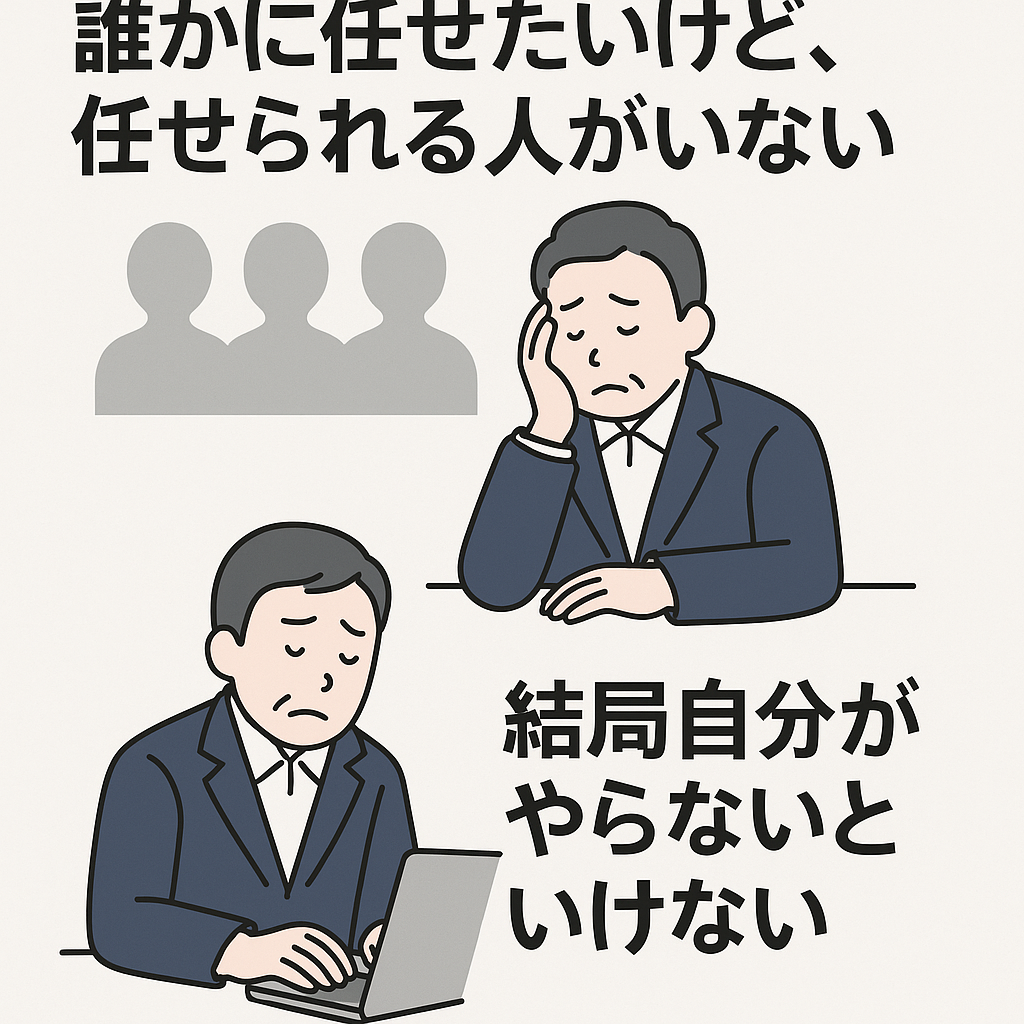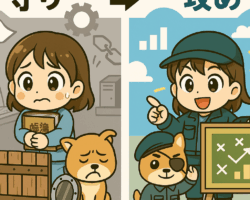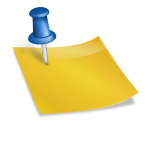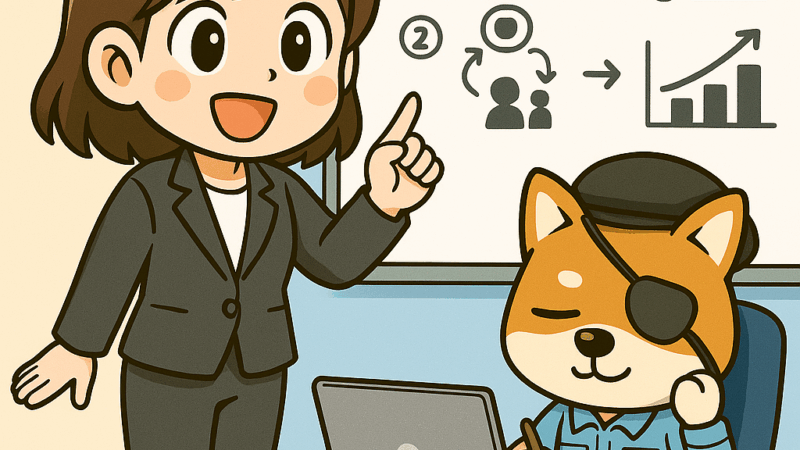外注で業務をスマートに!中小企業が見落としがちな「本当に効果が出る外注活用法」とは?
中小企業が直面する共通の悩み――それは「人手が足りない」「時間がない」「専門スキルが社内にない」という三重苦です。加えて、属人化した業務や引き継ぎの曖昧さが、日々の業務の非効率さやストレスを増幅させているという声も少なくありません。
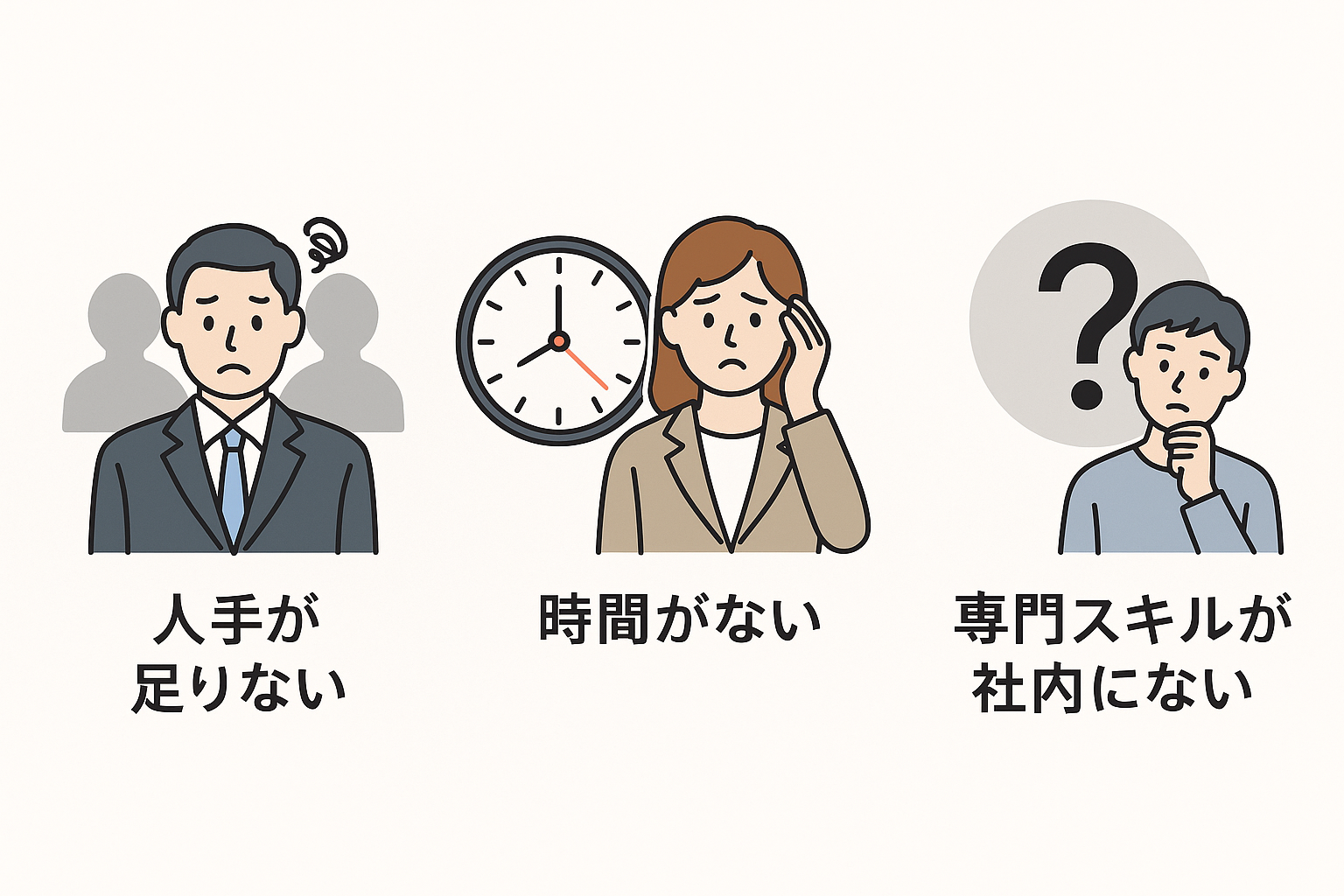
多くの中小企業では、社長や経営陣がプレイヤーとしても現場業務を担っており、「誰かに任せたいけど、任せられる人がいない」「結局自分がやらないといけない」という状況に陥っています。そこに少しでも風穴を開ける方法として、近年注目されているのが「外注(アウトソーシング)」という選択肢です。
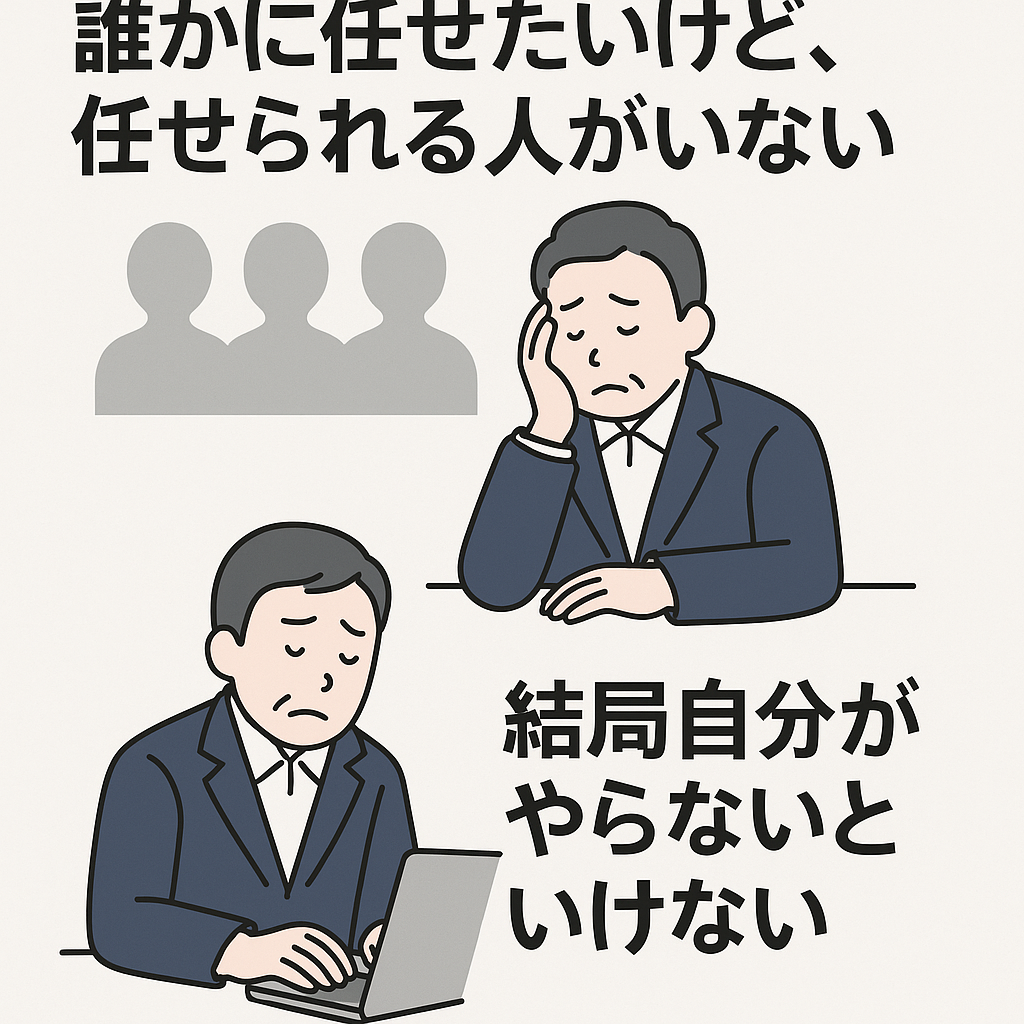
外注は、単なる「人手の補填」ではなく、専門性を持った外部のパートナーに“成果”を依頼できる仕組みです。経理や事務、ITサポートなど、限られた社内人員では手が回りにくい業務を、的確かつ効率的に進めることができます。
また、外注を導入することで、自社の業務そのものを見直すきっかけにもなります。今まで感覚的に進めていた仕事を言語化・構造化し、再設計することで、企業全体の生産性が向上しやすくなります。
さらに、外注は「緊急対応」にも有効です。たとえば「IT担当が急に退職した」「経理が長期休職に入った」など、突発的なトラブルに対しても、柔軟に対応できる体制をつくることができます。
この記事では、「外注を依頼するとはどういうことか?」という本質的な部分から、代表的な業務(ヘルプデスク・事務・経理・人事)の外注メリット、そしてそれらを統括して活用するための経営コンサル導入の重要性、最後に「いなかん」が提供するワンストップ対応の強みまでをご紹介します。
今後の業務のあり方に悩む経営者の皆さまにとって、「これならうちもできそう」と思えるヒントになれば幸いです。
 ② 外注を依頼しなければならない背景(拡充版)
② 外注を依頼しなければならない背景(拡充版)
② 外注を依頼しなければならない背景(よくあるご相談)
中小企業が「外注」という選択肢に踏み切る背景には、いくつかの“リアルな事情”があります。「社員数が増えた」「事業拡大をした」など前向きな理由もあれば、「人が辞めた」「誰もわからない」などの緊急性の高いケースも少なくありません。ここでは、実際にいなかんへ寄せられるご相談の中から代表的な背景を紹介します。
1. 今以上の売上や効率を求めた結果、業務の“壁”にぶつかる
事業成長を目指す中で、売上は伸びたものの、業務は人海戦術のまま…という企業は多くあります。特にバックオフィス部門は売上に直結しづらいため、投資判断が後回しにされがちです。しかし、管理部門が整備されていなければ、ミスや遅延が積み重なり、逆に利益を圧迫するリスクがあります。
2. 担当者が急に退職し、業務が完全に止まってしまった
「経理担当が退職し、次の人が見つからない」「社内SEが辞めてしまい、トラブル対応ができない」など、業務が属人化していたことで発生する“業務断絶”は非常に深刻です。特に中小企業では、1人が辞めることで業務の全体が麻痺することも珍しくありません。
こうしたケースでは、外注を導入することで一定の業務継続を確保しつつ、引継ぎや仕組みの再構築に取り組むことができます。
3. 今の会社規模以上を想定した体制構築のため
将来的な組織成長を見越して、「今のうちに業務を整理しておきたい」「人を雇う前に一部をアウトソースしたい」といった“準備型”の外注も増えています。これは非常に良い判断で、先に外注を導入しておくことで、採用・教育コストを抑えながら安定した成長が見込めます。
4. 新しい業務・専門的な仕事が増え、自社で完結できなくなった
DX、SNS運用、Web管理、クラウド導入など、近年急増している業務は、従来の事務担当や総務の役割を超えることが多くあります。これらをすべて内製化しようとすると、時間もコストもかかりすぎてしまいます。
外注なら、その道のプロに任せることで、短時間で質の高い成果が期待できます。特にいなかんのように、複数の分野を横断して対応できるパートナーがいれば、バラバラな発注先に頼らず一気通貫で解決することも可能です。
こうした背景があるからこそ、「業務の外注」は単なるコスト削減ではなく、“経営の仕組みづくり”としての意味を持つようになってきています。成長のスピードと柔軟性を保つためにも、ぜひ一度立ち止まって検討してみてください。
 外注は成果物に責任を持つ契約
③ 外注という手段の本質(拡充版)
外注は成果物に責任を持つ契約
③ 外注という手段の本質(拡充版)
③ 外注という手段の本質
外注と聞くと「人手を補うもの」として捉えられがちですが、実際にはそれ以上の価値があります。ここでは外注の“本質”について整理していきます。
1. 「人を増やす」ことと「外注」はまったく異なる
社内の人材を増やすというのは、人件費・育成コスト・管理負担が増えることを意味します。一方、外注は業務の成果や一定の役割を切り出して委託するもの。目的と成果が明確になっていれば、自社にとって必要な部分だけを効率よく補うことが可能です。
人を雇う場合には社会保険や福利厚生の管理も必要となりますが、外注であればそうした間接コストもかかりません。その意味で、コスト面でも明確な違いがあります。
2. 外注は「成果物に責任を持つ契約」
たとえば、経理業務の一部を外注する場合、「毎月○日までに請求書処理」「試算表作成」などのアウトプットに責任を持ってもらうことになります。
これは、単に“人が作業する”ということではなく、「成果を納品してもらう」という契約であり、質・納期・報告などのビジネス基準が明確になります。社内で“なんとなくやっていた”業務に対し、外注を入れることで可視化され、改善が促されることもあります。
3. 外注化を成功させるには“自社の課題”の明確化が必要
「誰に何を頼めばいいのかわからない」という状態では、外注してもうまくいきません。外注化とは、業務を明文化し、成果として渡すプロセスを整理することでもあります。
まずは自社で「どの業務が滞っているのか」「どんな業務が属人化しているのか」を洗い出し、“どの業務にどんな成果を求めているか”を言語化することが、外注を成功させる最大のカギです。
4. 成果志向の業務設計に近づくチャンス
外注を通じて、「この業務って実はここまでやらなくてもいいのでは?」「逆に、ここの確認フローが曖昧だった」といった改善点が見えてくることもあります。
つまり外注は、自社の業務を見直す「きっかけ」としても非常に有効です。依頼内容を整理し、外注先とのやり取りを通して、業務が“誰のために、何のためにあるのか”を再認識する経営者も少なくありません。
外注とは、単なる外部依頼ではなく、自社の中にある“本当に価値ある仕事”を選別し、洗練させるプロセスでもあるのです。
ただ人手を補うだけでなく、“業務設計そのものを見直し、経営戦略の一環として活用する”。それが、現代における外注活用のあるべき姿です。
 ④ ヘルプデスク外注のメリットと事例
④ ヘルプデスク外注のメリットと事例
④ 各業務別の外注メリットと事例:ヘルプデスク

Q. そもそも「ヘルプデスク外注」ってどんな仕事?
A. 社内のITトラブルやパソコン設定、ソフトの使い方、クラウドの運用サポートなど、従業員が日々直面する「ちょっとした困りごと」を外部のITサポートが代わりに対応するサービスです。システム担当がいない企業にとっては、社内SEの代替としても機能します。
よくある外注内容とは?
- パソコン・プリンターの設定
- メール設定、ドメイン管理
- クラウド(Google WorkspaceやMicrosoft365など)の導入支援
- 社内ネットワークやVPN接続のトラブル対応
- 業務アプリの初期設定や操作レクチャー
いくらくらいで依頼できるの?
ITに関する外注はピンキリですが、一般的なWeb制作会社やITサポート会社では、月額5万円〜15万円程度が相場です。スポット対応であれば1回あたり1〜3万円程度というケースもあります。
ただし、IT分野は“料金が高くなる”と思われがち。いなかんでは、月3万円台からのライトプランもご用意しています。
詳細はこちら:社内SE・web制作・ヘルプデスク外注の詳細はこちら
導入事例:IT担当が突然退職…でも業務は止められない
所沢市の中小企業A社では、長年勤めていた社内SEが退職し、後任が決まらないまま日常業務に支障が出ていました。いなかんにご相談いただき、初回ヒアリングの翌日には社内のIT環境調査と整理を実施。
その後、Googleアカウントの管理、メール設定、プリンターの接続など日常業務を「即日で復旧」させ、現在も月額契約でリモート&定期訪問対応を継続中です。
詳細はこちら:ヘルプデスク外注の実例を見る
ヘルプデスクは「トラブルが起きてから考える」では遅い分野です。いなかんの外注サービスなら、必要なときにすぐ頼れる“社外ITチーム”として、御社を支えることができます。
⑤ 各業務別の外注メリットと事例:事務代行
⑤ 各業務別の外注メリットと事例:事務代行

Q. 「事務代行」って、具体的にはどんな業務を頼めるの?
A. 請求書の発行・チェック、書類整理、データ入力、電話・メール対応、来客対応など、日々の細かいバックオフィス業務を外注することができます。特に、時間がかかるのに専門性は不要という業務の“切り出し”に向いています。
よくある事務代行の業務内容
- 請求書の発行・管理
- 書類のファイリング・スキャン
- メール代行・郵送物の対応
- 簡単な入力作業やデータ整理
- 備品の発注・在庫管理
費用の相場感は?
1日数時間の対応であれば、月額2万円〜6万円程度が一般的です。スポット対応であれば1時間あたり2,000〜4,000円が相場です。
「社員を雇うほどではないが、事務処理の負担を軽くしたい」という会社に特に人気があります。
導入事例:経理・事務が同時に不在になったA社のケース
入間市のB社では、経理・事務を兼務していた社員が退職。社長が自ら請求書作成や郵送対応までしていたが、「本業に手が回らない」と相談をいただきました。
そこで、いなかんが事務代行を週2回ペースで導入。月末月初の繁忙期を中心に対応し、経理や税理士との連携もしながら業務をスムーズに再構築。結果として、社長の業務負担が月30時間以上軽減されました。
詳細はこちら:事務代行の導入事例を詳しく見る
「事務作業が面倒」「片付ける時間がない」と感じている方には、事務代行は非常に有効な選択肢です。
特に、いなかんでは柔軟な対応時間・業務カスタマイズが可能なため、必要なときだけ依頼できる点もご評価いただいています。
⑥ 各業務別の外注メリットと事例:経理代行
⑥ 各業務別の外注メリットと事例:経理代行

Q. 経理代行ではどんな業務を任せられるの?
A. 主に会計ソフトへの仕訳入力、請求書の発行・処理、月次・年次資料の作成、領収書の整理、振込データの作成など、日々の経理業務全般を外注できます。税理士と連携した支援も可能です。
よくある業務内容
- 仕訳入力(会計ソフト:弥生・freee・マネーフォワードなど)
- 請求書の作成・送付・入金確認
- 領収書のスキャン・整理
- 銀行振込データの作成
- 月次試算表・決算資料の下準備
費用の目安
業務量にもよりますが、月額3万円〜10万円程度での外注が一般的です。完全外注よりも、社内対応+外注のハイブリッド型が選ばれることも多く、業務範囲によって調整が可能です。
導入事例:売上管理が追いつかず請求ミスが続発していたC社
所沢市のC社では、営業が兼任していた経理業務で請求漏れ・金額ミスが頻発していました。いなかんが月次の経理代行として介入し、会計ソフトの仕訳入力から、請求書の自動発行・入金管理までを再構築。
ミスが激減しただけでなく、税理士との連携資料も整い、月末対応のストレスも大幅に軽減されたと好評をいただいています。
詳細はこちら:経理代行の事例を見る
経理は、数字を扱う仕事だけにミスが致命的になる領域。だからこそ、専門性のある外部パートナーに任せることで、安心と時間の確保につながります。
⑦ 各業務別の外注メリットと事例:人事・求人代行
⑦ 各業務別の外注メリットと事例:人事・求人代行

Q. 人事や採用活動まで外注できるの?
A. はい、求人募集から応募者管理、一次対応、面接調整まで、採用に関する業務の一部または全体を外注することが可能です。特に、専任の人事担当がいない中小企業では有効な手段として活用されています。
どんな業務が依頼できる?
- 求人原稿の作成・掲載(Indeed、求人ボックスなど)
- 応募者対応(メール返信・電話受付など)
- スケジュール調整・一次面談の代行
- 採用媒体の選定と運用代行
- 社内の人事制度設計支援
導入事例:応募は来るのに採用につながらなかったD社
川越市のD社では、求人は掲載していたものの「応募が来ても対応が遅れ、採用に至らない」という課題を抱えていました。いなかんでは、求人媒体の見直しから応募者対応のフロー設計、一次面接の代行までを実施。
結果として、対応スピードが大幅に改善され、3ヶ月で2名の採用に成功。採用担当不在でも「採れる体制」が構築されました。
人事×経営の視点が鍵になる
採用は単なる作業ではなく、企業の未来をつくる重要な投資活動です。だからこそ、「どんな人材を、どんな役割で迎えるか」という設計が極めて重要になります。
いなかんでは、経営戦略に合わせた「採用計画」も含めてご提案可能です。求人票ひとつとっても、「会社の魅力が伝わるかどうか」が採用成功を左右します。
人事業務を外注することで、「会社の軸」がより明確になり、採用だけでなく定着や育成の面でも良い循環が生まれやすくなります。
⑧ 外注は「点」でなく「線」で考えるべき
⑧ 外注は「点」でなく「線」で考えるべき
多くの企業は、まず「困っている部分」をなんとかするために外注を検討します。たとえば、「経理担当が辞めた」「クラウドの設定が分からない」「求人に人が集まらない」など、“ピンポイントの課題”に対して外注が導入されがちです。
もちろんそれ自体は大切な判断ですが、外注は単なる「応急処置」ではなく、もっと大きな視点で捉えることで本当の効果を発揮します。
点の依頼だと、連携不足や二重作業が発生する
例えば、経理は外注しているが、請求書の発行は社内で手作業。人事は求人だけ外注しているが、入社後の手続きは社内で混乱…というケースはよく見かけます。
これでは業務が“つながっていない”ため、どこかで抜け漏れや非効率が発生しやすくなります。
外注を「線」で設計する=業務フローとして統合する
ヘルプデスク・事務・経理・人事…それぞれを個別に考えるのではなく、「どうやって1つの流れとして連携させるか」という視点が、これからの時代には必要です。
いなかんでは、外注先を「部分的に切り出す」のではなく、会社の全体像や今後の成長を見据えて、「流れ」として設計する支援を行っています。
開業支援から一貫対応できるからこそ、無駄が出ない
特に新規創業・法人化のタイミングでは、「何から始めたらいいかわからない」というご相談を多くいただきます。いなかんでは、開業支援から経理・事務・IT・人事の設計まで、ワンストップで対応可能です。
外注を点ではなく“線”で導入することで、コストも業務設計も、最初から無駄のない体制が整います。
詳しくはこちらの事例もご覧ください:
開業支援の事例を見る
⑨ 経営コンサルタントの導入でどう変わるか
⑨ 経営コンサルタントの導入でどう変わるか

ここまで、さまざまな業務を「外注する」ことのメリットをご紹介してきましたが、それらをバラバラに導入していては効果は限定的です。そこで必要となるのが、「外注の設計図」を描ける存在――それが経営コンサルタントです。
部分最適ではなく、全体最適を実現する視点
経理だけを外注しても、売上管理の仕組みが古いままではデータが活かされません。ITサポートを外注しても、社員がツールを使いこなせなければ業務は改善されません。こうした“つながりのない改善”を防ぐためには、全体を見渡しながら各業務をどう設計・連携すべきかを導く力が不可欠です。
「経営」と「人」の両面を見られる専門性
経営コンサルタントは、単なる業務改善だけでなく、「人材=人財」をどう活かすか、という視点も持ちます。採用戦略、配置、教育など、経営の根幹を支える“組織”の設計も担う役割があります。
特に中小企業においては、社長や少数の幹部がプレイヤーとしても動くことが多く、「全体設計を考える余裕がない」というケースが大半です。そうした企業こそ、外部の専門家の視点で設計図を整えることが必要です。
本当に必要なのは「人を増やす」ことではない
忙しくなった=人を雇う、という発想は危険です。業務を可視化し、分業化・効率化することによって、むしろ人を増やさずに事業を拡大できる余地は多く残っています。
経営コンサルタントは、“会社の未来に必要な仕事”を抽出し、再構築するサポート役でもあります。
経営の“外科医”として、部分ではなく全体を診る。この役割が、外注時代における経営コンサルタントの価値です。
⑩ 各サービス紹介+リンク挿入
⑩ いなかんの各サービス紹介
1. 経営コンサルタント
業務改善だけでなく、会社全体の仕組みづくり・人事戦略・バックオフィス統合など、戦略的な経営のサポートを行います。外注を“点”でなく“線”で活かす体制構築が可能です。
▶ 詳しくはこちら
2. バックオフィス代行(事務代行)
書類整理・郵送物対応・備品発注・請求書作成など、日常の事務業務をアウトソーシング。時間を生む仕組みをご提案します。
▶ 詳しくはこちら
3. 社内SE・Web制作・ヘルプデスク外注
ITトラブルの解決・Webサイトの運用・GoogleやMicrosoftアカウントの管理など、社内にIT担当がいなくても“まるっと”サポート。
▶ 詳しくはこちら
4. 経理代行
会計ソフト入力・請求処理・領収書整理・振込準備など、日々の経理業務を正確&効率的に処理。税理士との連携も対応可能。
▶ 詳しくはこちら
5. 広告代理事業・SNS運用
SNS(Instagram・Xなど)の運用代行やバナー制作、広告運用まで対応可能。中小企業の“集客力”をデザインから支援します。
▶ 詳しくはこちら
▶ いなかんサービスに関するご相談はお気軽に!
サービスの詳細や導入事例、無料相談のお申し込みは以下のページから可能です。
お問い合わせフォームはこちら
【番外】バックオフィス外注 国内の現状と展望
バックオフィス外注 国内の現状と展望【番外】
概要:本レポートは、日本企業におけるバックオフィス業務の外注化(BPO)の現状・市場規模・企業規模別の導入状況・促進要因・効果・課題・今後の展望について、豊富な客観的データに基づき、最新の図表も交えて詳細解説します。
2024年6月版
1. 序論:バックオフィス外注化の概要と重要性
近年、企業の競争環境が激化し、事業効率の向上や人材不足対策のために「バックオフィス業務(経理・人事・総務・労務など)」の外注化が急速に進んでいます。これを包括的に担うのが
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)です。BPOでは単純な業務代行にとどまらず、業務プロセス設計やDX(デジタルトランスフォーメーション)も重要な要素になっています。
外注化によって、企業はコア業務への集中・コスト削減・業務効率化・ノンコア業務の専門化など多くのメリットを享受できる一方、適切なマネジメントやリスク管理、企業文化との適合も欠かせません。本レポートは、こうしたバックオフィス外注化の日本国内における最新事情をデータとともに明らかにしていきます。
2. 日本のBPO市場の現状
市場規模と推移
日本のBPO市場は
2022年度:4兆7,020億円(前年比3.0%増)
(出典:矢野経済研究所・オフィスのミカタ 2024)
と推計され、近年右肩上がりで拡大を続けています。業種・業態を問わず、バックオフィス業務の効率化・DX化・人手不足対策としてBPOサービス活用が進んでいます。
- 2021年度:約4兆5,637億円
- 2022年度:約4兆7,020億円
- 2023年度(予測):約4兆8,410億円(+2.9%)
IT系BPOと非IT系BPOの内訳
- IT系BPO:システム開発保守、インフラ管理等(市場規模:約2兆7,000億円)
- 非IT系BPO:経理、人事、総務、事務プロセス等(市場規模:約2兆円)
IT系BPOはDX需要拡大、非IT系BPOは労務・人事・経理の効率化需要に牽引されています(出典:矢野経済研究所, 2022)
国際比較からみる日本の状況
世界的に見ても日本のBPO市場規模は大きいですが、GDP比では欧米やインドなどアウトソーシング先大国と比べて
日本企業のBPO活用率はまだ中位水準にとどまります。特に中小企業の導入率が低いことが、今後の成長余地とされています。
| 国名 | BPO市場規模(USD) | GDP比 |
| アメリカ | 約1200億ドル | 1.8% |
| インド | 約600億ドル | 3.1% |
| 日本 | 約350億ドル(4.7兆円) | 0.8% |
(各国主要調査会社・政府統計より換算、2022-2023年)
3. 企業規模別の外注化状況
大企業 vs 中小企業の導入率の違い
大企業(従業員500名以上):外注化率は約50%
中小企業(従業員300名未満):外注化率は12.9%
(2025年 パーソル調査)
- 従業員100~299人:24.6%
- 従業員10人未満:6.9%
企業規模による課題の違い
- 大企業:仕事の属人化、人手不足、業務の範囲拡大
- 中小企業:業務マニュアルの未整備、担当領域が多い、外注管理負荷
(出典:株式会社GOOD PLACE・パーソルビジネスプロセスデザイン、2024~2025年調査)
4. 外注化されている業務分野の詳細分析
業務別の外注化率
- 経理・財務:29.6%
- 労務(社保手続など):26.8%
- 人事(管理含む):19.7%
- システム/インフラ開発・構築/運用:16.9%
※複数回答(n=71、パーソル調査)
業務特性と外注化の相関関係
- 専門性・定型化度が高い業務: 経理・給与計算・システム保守等は外注化率が高い
- コア業務・意思決定・営業等: 外注化率が低い
- 属人化・法令順守・繁雑なルーティンは外注化候補となる一方、企業独自の業務や高度な判断を伴う業務は内製志向が強い
5. 外注化を促進する要因
人手不足の影響
日本の生産年齢人口は2020年から2065年に向けて約29%減少と推計されており、企業がバックオフィス人材確保に苦慮している実態があります(総務省統計)。
デジタル化・自動化の必要性
電子帳簿保存法やデジタルインボイス等、法制度によりデジタル対応が必須化。BPOベンダーには専門知見やツール活用力が求められています。
働き方改革との関連性
時間外労働の規制、派遣法改正等により社内人員だけでの運用が困難となり、BPO導入が進みました。
6. 外注化の効果と導入事例
コスト削減効果
- 月額10万円未満での外注事例が最多(中小企業)
- 経理・人事など専門職を正社員雇用するよりも安価で経済的負担を分散できる
業務効率化の実績
- 従業員の負担が軽減され「はたらきやすい環境が整った」:21.1%
- 業務コスト削減:19.7%、効率向上・業務量増への対応:16.9%
導入事例
- 事例A(中堅メーカー): 労務手続き・給与計算をアウトソーシングし、経理部の残業時間が月40時間→10時間に短縮
- 事例B(ベンチャー): 経理BPO導入で属人化を解消、法令対応・決算の早期化も実現
7. 外注化の課題と障壁
コスト面の懸念
- 「結果的にコストが高くなる」:24.4%(未導入企業、パーソル調査)
- 外注先の品質により総コストが変動する場合も
情報セキュリティリスク
- 個人情報、機密データの漏洩防止策・認証取得状況確認が不可欠
人材の処遇問題
- 従業員の配置転換・モチベーション低下など社内体制への配慮も必須
8. 今後の市場予測と展望
成長分野の予測
- BPaaS(Business Process as a Service)などSaaS+BPOのクラウド型サービスが急拡大
- 人事・給与・会計・法務のデジタルアウトソーシング需要拡大
技術革新の影響
- AI・RPA活用による省力化、BPOベンダーの競争激化
国際競争の視点
- オフショアBPOの活用進展(アジア圏)
- 日本は法制度対応・セキュリティ・言語要件から内製志向も底堅い
9. 企業への提言
外注化検討のためのフレームワーク
- 業務棚卸し・定型化度・属人度の可視化
- コア業務/ノンコア業務の切り分け
- コスト試算およびBPO/自社内製の費用対効果比較
- 外注先の品質・体制・セキュリティの審査
成功のための実施ステップ
- 段階的な業務移管(まずは一部業務から委託)
- 進捗・成果の可視化管理
- ナレッジ・ノウハウの社内共有体制維持
- 社内従業員への適切な配慮と説明
10. 結論
日本のバックオフィス業務の外注化は、人口減少やDX推進などの追い風を受け年々拡大しています。
中小企業の導入はまだ低いものの、BPaaSなど新型サービス登場を背景に今後も伸長が予想されます。
企業は、BPO活用の効果とリスクを理解し、自社の実情・課題に合った最適な外注戦略を検討する必要があります。
矢野経済研究所「BPO市場に関する調査(2022-2024)」, 総務省・内閣府 各種統計